2026/01/20
AIが初心者の参入障壁を下げる!? 〜家庭菜園・ガーデニングの新しい楽しみ方〜
2025/07/23
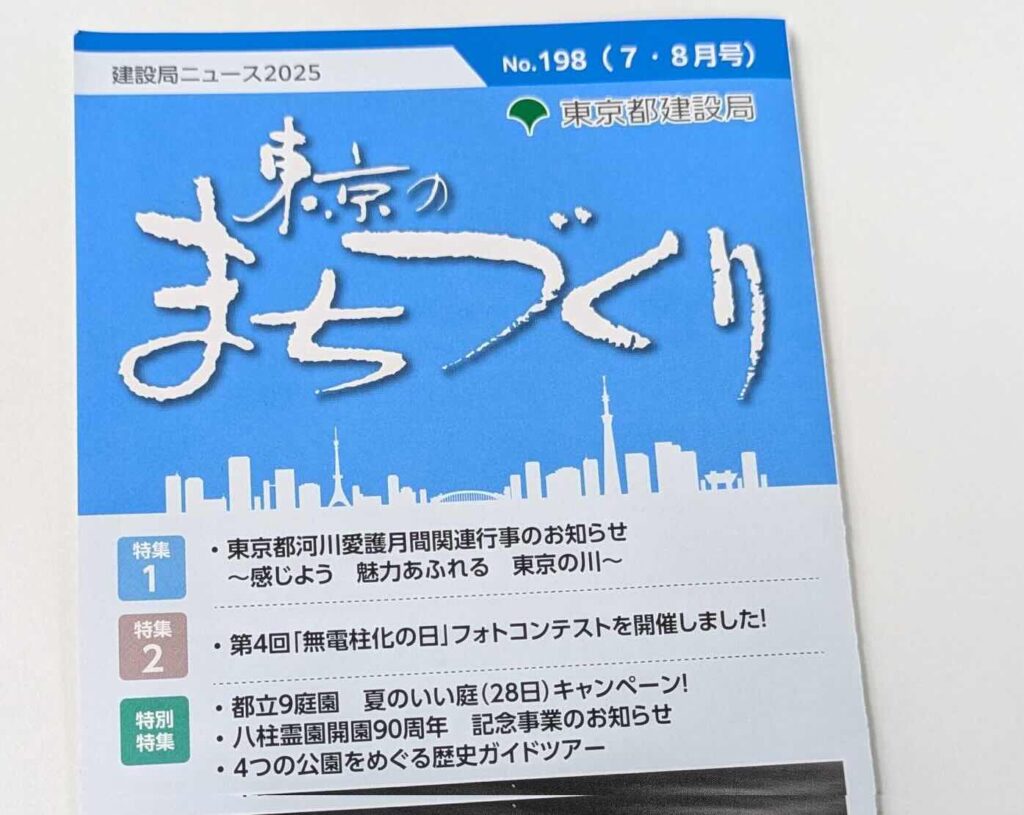
代表コラムです。また例によって少し間が空いたかもしれません。選挙が衝撃的だったのでというのはいいわけです。
ノンフィクションやドキュメンタリーが好きです。戦場の無惨な現実や探検の記録といった非日常的なドキュメンタリーも好きですが、NHKの72時間のような一見ありふれているような日常を切り取って、平凡な中に存在する埋もれた価値を再発見してくれるようなものもよいですね。フィクションでは得られない、現実の持つ程よい重さがもたらす養分があるような気がします。
普段貧乏暇無しで慌ただしく暮らしていると、ふと立ち止まって振り返る時間を持ちたくなるものです。特にスマホ社会の今日、電車の中でSlackチェックしたり慌ただしくなると精神が容易にくたびれてしまいます。電車に乗る間はスマホを触らずにいられないだろうかと思いますが、しかしいささか活字中毒の私は、スマホを触らないと決めるとつい社内の吊り広告に目が向います。しかしあんまり面白くない。飽きてくると周囲の人の人間観察を始めたりして十分に不審者です。これはまずい。
そんな気分で、先日地下鉄に乗ろうとした矢先に、東京都のリーフレット置き場が目につきました。最寄りの内幸町は都営三田線なので東京都や関連する公的団体のリーフレットがたくさんありました。なんとなく取ってみるとこれが面白いです。今日はその中でも東京都建設局の発行する「東京のまちづくり」をご紹介したいです。もちろんネットでも見られます。
大学院までは「まちづくり」を専攻していたことになっているのですが、私の関心はもっぱらソフトウェアとしての計画に絞られていました。周りの学友がハードの構成に興味を持っていたのに比べると少し特殊だったかもしれません。しかし齢を重ねると若い頃にはあまり興味を持てなかったことに案外興味を持てたり、重要性に気づいたりすることもよくあります。まちのハードウェアもその一つで、一都三県にわたる東京都市圏は世界レベルで見ても極めて高レベルな交通、水流、情報、安全システムを誇る巨大な都市システムだと思います。昨今の灼熱化する日本列島の中で、その中で暮らして仕事をしていることがありがたく感じるようになりました。
さて、手に取ったのは東京のまちづくりNo.198(2025年7・8月号)でした。表紙の左肩に建設局ニュース2025とあるので、これが正式名称なのかもしれません。年内には200号になりそうですが、年間6本発行として逆算すると33年前の1992年頃が第一号になりそうです。ちょうど私の大学生の時代。その頃から比べると地下鉄と周辺の私鉄路線の接続も劇的に改善したりと、大きく東京が進化していることが思い出されます。
特集によると、7月は河川愛護月間ということで、川に関するイベントが多数開催されています。かつての東京といえば神田川の氾濫や荒川放水路の事業で知られるように水害で苦しめられたイメージですが、最近はかなり穏やかになったような気がします。(とはいえ先日の目黒川はすこし危なかったかもしれませんし、記憶をたどると2019年の二子玉川の水害など忘れてるだけかも。。。)
河川愛護月間の関連行事はフォトコンテスト、土砂災害の防止の絵画・作文募集などコンテンツ募集と実際の川を歩くイベントなどがあります。時間があればぜひ参加してみたいですが、土曜の9:30に行くことのできる、つまりは元気な人向けということになりそうです笑。
長くなりましたのでそろそろ終わりたいですが、地味系リリースがいいですね。国分寺3・2・8号府中所沢線が460メートルが交通開放されたということで、白バイの写真が乗ってます。西武国分寺線は乗ったことありませんが、先日小田急から西武鉄道がエコな中古車両を購入して、国分寺線のような支線に投入するというニュースを見ました。そういうローカルな都道が徐々に整備されて交通渋滞がゆっくりゆっくり改善するのが東京の日常なのだと思いました。
あと夢の島熱帯博物館のニュースもありました。すでに展示期間を終わろうとしてますが、特別な熱帯夜ということで、普段は17時00分終了の熱帯植物館が20時30分まで入れるとのことです。そういえば夢の島熱帯植物園もあったなと思い出しました。東京は美術館や動植物園などが大変充実しているのですが、数が多すぎてつい想起されなかったりするのも我々のくらす東京の豪華さを象徴しているような気がしました。
ぜひ皆さんも東京のまちづくりを手にしてみてください。

