2026/01/27
パッケージ型ネットリサーチ「ニーヨン」、AI分析機能を搭載し正式版をリリース。調査完了と同時に「要約・対話型分析」を提供
2025/07/28
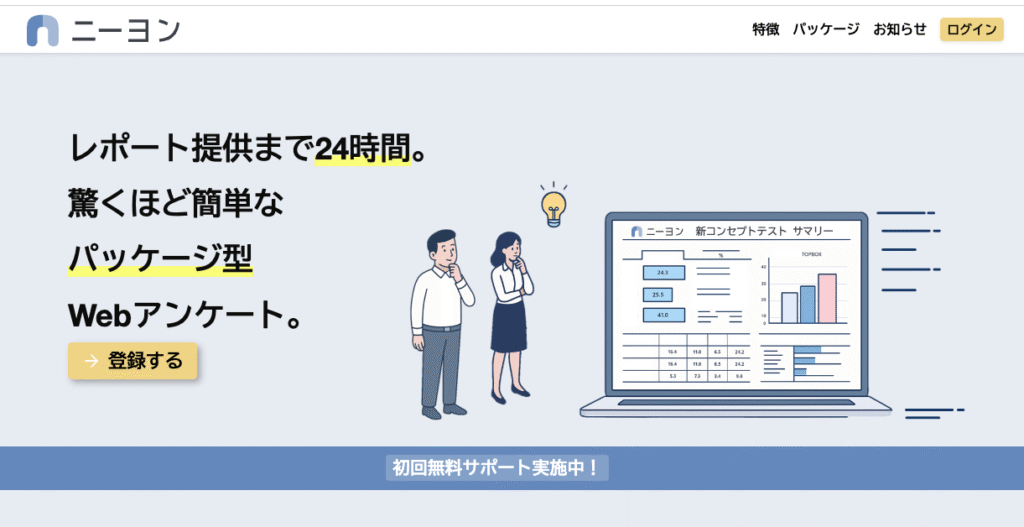
灼熱の日本列島ですが皆様ご自愛ください。代表コラムです。
Webシステムの世界では、DevOpsという言葉があります。
ご存じない方に説明すると、もともと(20年ぐらい前?)のWebシステムは開発がとても大変でした。
データベースは高価で、プログラムはJava ServletでコンパイルやWebサーバとの接続設定が大変だったり。プログラムが動作するサーバを一つ一つ設定したり。そういう中で、「開発」(Dev:Devevelopment)と「運用」(Ops:Operations)が分離していました。
開発は純粋にプログラムを開発すること。運用はそのプログラムをユーザ提供するうえで必要な環境構築やメンテナンスを行う。そんな役回りだと思っていたらよいかもしれません。正確な説明になっている自信はありませんが。。。
しかし、その中で「マシンの仮想化」というトレンドがやってきます。大きな物理的コンピュータの上に複数のOSを必要に応じて立ち上げたり削除したりできる技術です。これにより運用環境と同じような環境でプログラムを開発できるようになり効率的になりました。その中で、運用環境を開発環境で再現するための技術が進化してきます。今はDockerという技術が支配的です。Dockerのような仮想化ソフトを使うことで、物理的マシンの中で様々なアプリケーションを「コンテナ」と呼ばれる単位で(プログラム的に)管理することが一般になったのです。
また、AWSのようなクラウドの登場により、Webサービスを支えるインフラも様々に進化しました。Lambdaに代表されるサーバレス技術など、必要に応じて使いたいツール群を組合せて最適なアプリケーション構成を高速に実現する。そんな技術です。
そのような技術的背景を元に、運用(Ops)側の負担をなるべく軽くするように、開発と運用一体的に考える。そんなトレンドが生まれました。それがDevOpsです。
一口に言ってしまえば、開発にあたりそれが提供される環境も考慮しながら高速にサービスを提供する動き。として整理されるかもしれません。
DevOpsが一般的に受け入れられるにつれて、最近ではMLOps(プログラムの化初の代わりに、機械学習(Machine Learning:ML)やAI活用業務の設計に当たり運用を考慮するトレンド)なども検討され始めています。このような考慮が進めば進むほど、組織内部でのAI活用が高速に進むことは当然で、高度なエンジニアリングリソースも必要である一方で、構築されることによるメリットは計り知れないと思います。
一方で、DevOpsが社内外のシステムの運用を効率化し、システム活用の場面を増やしてきたのと同じように、リサーチももっと組織の中で活用されるべきではないか?とリサーチ会社にいる私は思っています。マーケティング組織として新しい商品やプロモーション手法の開発が日々求められていく中で、それらの事前評価やもっとも望ましい施策を選択していくためには、リサーチこそもっと社内で活用していかなければなりません。しかし、今リサーチを実現しようとすると、担当者が考えなければならないことも多く、調査会社に相談するのも大変だし、時間もかかる。そんな中でResearchをより組織内で普及させていくために、なるべく少ないコストでリサーチの実施・運用フェースが運用できなければならない。
そのためのキーコンプトがResearchOps(ResOps)です。
アイデア開発や新商品開発の現場に寄り添ったリサーチの実現には何が必要か。
まずは評価したいアイデアやコンセプトの標準的なフォーマット化や結果評価のための仕組み、ノルムの蓄積などがすぐ思いつくところです。
また、アイデア作成はアイディエータをぜひ使ってください。
検索したらUXリサーチの文脈ですでに考えていらっしゃる方もいるようです。
ユーザーリサーチの仕組みを整備する『ResearchOps』はじめます|イノツメ タケシ / DesignOps / デザインプログラムマネージャー
素晴らしいですね。
もちろん理想のResOpsにむけて弊社も考えています。今日本で一番手軽に市場調査を実施できるツールはニーヨンです。(私調べ)
調査したいテーマやキャンペーンなどをご準備いただければ、5分後に調査が始められ、24時間後にはレポートがお手元にダウンロードできる仕組みです。
ぜひご活用ください。
