2026/01/20
AIが初心者の参入障壁を下げる!? 〜家庭菜園・ガーデニングの新しい楽しみ方〜
2025/07/31
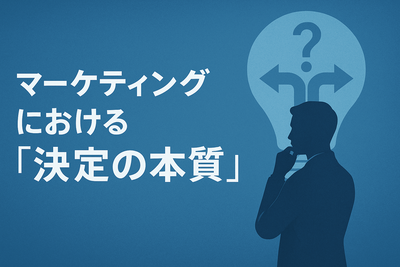
いろいろ必要があって、マーケティングの教科書的を紐解く機会があった。
ちょっと偉そうに聞こえるかもしれないが、マーケティングの教科書に書いてあることはどれも基礎的でありふれていることばかりに感じる。こんな事言われなくても少し考えればわかるだろう。ぐらいの事が多い。
例えば、AIDMAモデルで言えば、人が何らかの財を購入する際に「知る」「興味を持つ」「欲しくなる」「記憶する」「行動(購買)する」といった具合である。そもそも人間は知らないものは買えないし、興味を持ってないものを買うこともないだろう。言われてみれば至極当然の理屈である。
しかし、いざ自分のビジネスにおけるマーケティング活動を考えて、自信を持って十分な戦略性と効果的な戦術で満足しています。という人はそれほど多くない。有り体に言えば理論と実践との間でかなりのギャップが有る。そこがマーケティング・サイエンスの面白さであり未発達・未開拓な部分だ。学術的に言えば理論のレベルが低いと言うことになるのだろう。理論が現実を一定程度説明できるだけの材料やフレームが有るかというと心もとないのが率直な印象である。しかし、そもそもマーケティングという活動の歴史がせいぜい産業革命以降の200年ぐらいしかなく、さらにその間に発生した情報通信革命により「モノの売り方」方法論が大きく変化している中で、その他の多くの社会科学と同じようにまだまだこれからという方が妥当ではないか。
そんな中でマーケティングの実践における難しさとして一つの説明を作りたい。
政治過程論の分野では「決定の本質」でグレアム・アリソンがキューバ危機を鮮やかに分析しているように、同一の行動であってもいくつかの理論モデルにより異なる解釈が示されている。すでに今から半世紀ほど前の話である。
アリソンはキューバ危機を巡る各種アクター(登場人物)の動きを1)合理的モデル、2)組織過程モデル、3)政府内政治の3つのモデルで説明している。順番としては1)合理的>2)組織>3)政府内政治の順で思考するモデルのサイズが小さくなっていく。これは政府のような大きな組織ではその観察する事象のレベルにより求められる説明要因が異なるということを端的に示している。
例えば合理的モデルであれば、キューバにミサイルを持ち込まれたというアメリカにとっての核戦争危機を感知し、核戦争の回避やその他の政府目標を達成すべく、合理的に行動するとされる。ひょっとするとマーケティングの教科書に書いてある説明モデルのレベルはそれに近いかもしれない。みな「合理的に行動するとすれば」という前提の中で行動がわかりやすく解釈され説明される。
一方でもっともミクロな政府内政治のモデルで言えば、キューバ危機の大半のアクターは政治的プレイヤーであり、常にライバルとの緊張関係の中で様々な事案を処理していることになる。いくらキューバ危機が自国にとって存亡の危機であったとしても、眼の前の政治的闘争の具として利用するというのが政治屋の習いである。ちょうど今惨敗した自民党総裁の石破総理が辞めるやめないで、得票はそれほどでもなかったが、石破さんはやめてもらいたくない。みたいな分かりづらい状況が発生している。それと同じようなものかもしれない。
そのようなミクロな目線で言えば、誰もが自分が可愛く、いかに合理的かつ冷徹に(教科書的に)物事を考えよう。としたところで無理があり、「これは社長の命令だから」みたいな理由により陳腐な戦術が実行に移され、また自身の誤りを認めなくないトップは原因を別のところになすりつけるものだ。そんなことによりマーケティングの現場は極めて政治的に混乱した環境の中で展開される。というのが私の見立てである。だからこそ凡百のマーケティングはうまくいかないのではないか。
そうつらつら書きながら、じっと手を見る私がいる。
